歯ぎしりとは
歯ぎしりとは
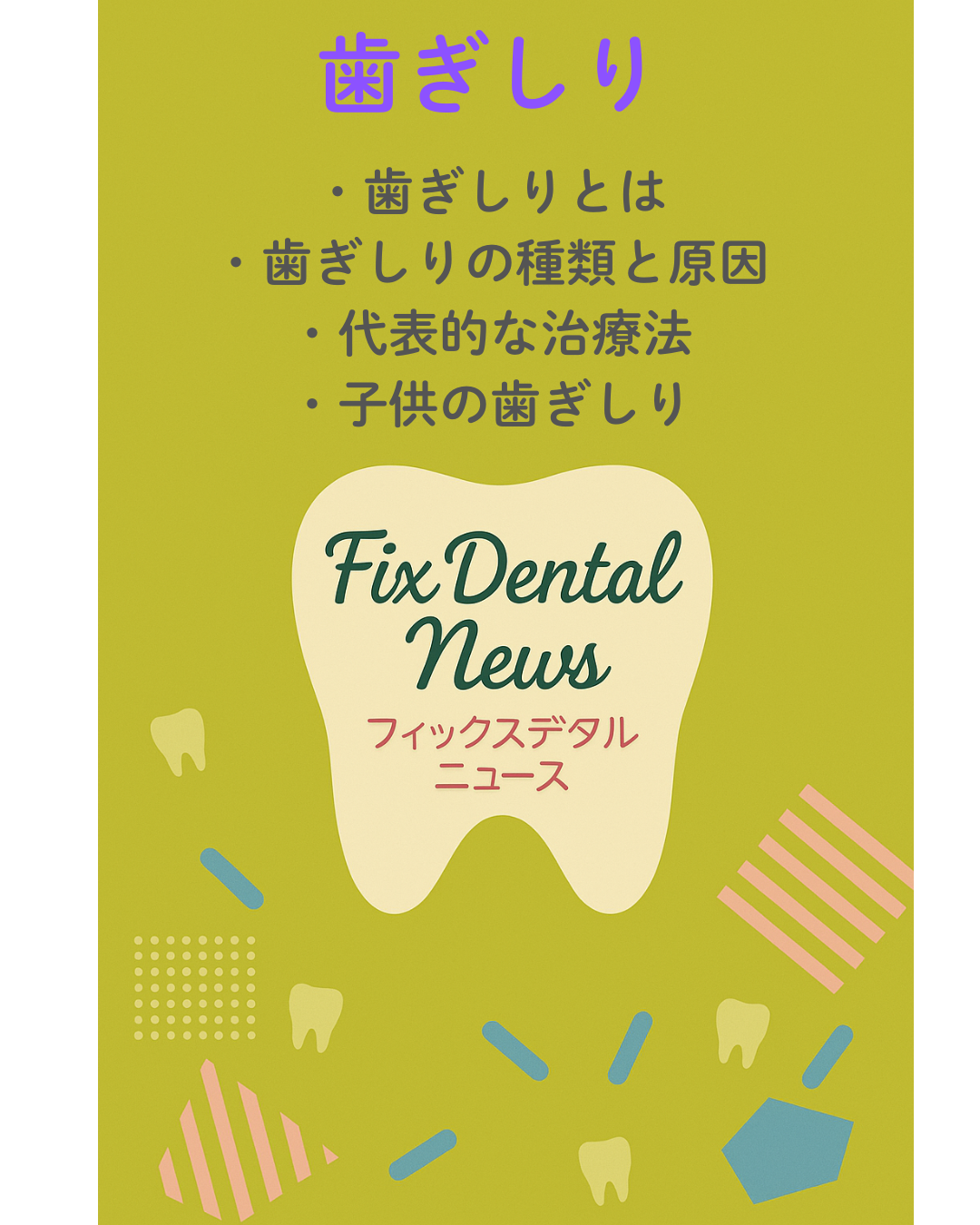
「寝ている間に歯ぎしりしているよ」と言われたことはありませんか。
無意識にしている歯ぎしりや食いしばりは、実は多くの人が経験していて、めずらしいことではありません。
歯ぎしりのしくみ

歯ぎしりは医学的に「ブラキシズム(Bruxism)」と呼ばれます。
上下の歯を強くすり合わせたり(グラインディング)、噛みしめたり(クレンチング)する習慣のことをいいます。
主に睡眠中に起こることが多く、本人は自覚しにくいのが特徴です。
歯ぎしりはなぜ本人にわからないの?

睡眠中に無意識で行っている事例が多いため、自分では気づきにくいのです。
家族に「歯ぎしりしていたよ」と言われて初めて知る人も多いでしょう。
また、日中でも緊張や集中時に食いしばりをしている人も少なくありません。
どのくらいの人がしているの?
一般的に、子どもの約3割、成人の約1割にみられるといわれています。
多くの場合は一過性で問題にならないことが多いですが、長期的に強い歯ぎしりを続けると、歯や顎に悪影響を及ぼします。
歯ぎしりは病気なの?
通常、睡眠中の歯ぎしりは健康障害がなく、病気とはみなされません。
ただし、強い力がかかり続けると歯がすり減ったり、かけたり、顎関節症を起こすことがあります。
そのため、予防や対策が必要な場合もあります。
歯ぎしりはなぜ起こるの?
原因ははっきり解明されていませんが、以下の要因が関わっていると考えられています。
- ストレスや緊張
- 噛み合わせの不調和
- 睡眠障害
- 飲酒や喫煙、カフェイン摂取
- 薬の副作用
歯ぎしりによる影響
歯ぎしりや食いしばりは、歯や口腔にさまざまな悪影響を及ぼします。
歯への影響
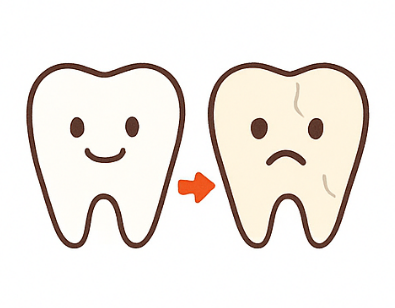
- 歯のすり減り、欠け、折れる
- 詰め物や被せ物の脱離
あごへの影響

- 顎関節症(顎の痛み、音がする)
- 噛む筋肉の疲労や痛み
全身への影響
- 顔面痛・耳鳴り・頭痛・肩こり・腰痛
- 睡眠の質の低下(熟睡できない)・倦怠感・自律神経失調症
歯ぎしりの種類と原因
歯ぎしりの種類には、大きく分けて3つのタイプがあるといわれています。
グライディング
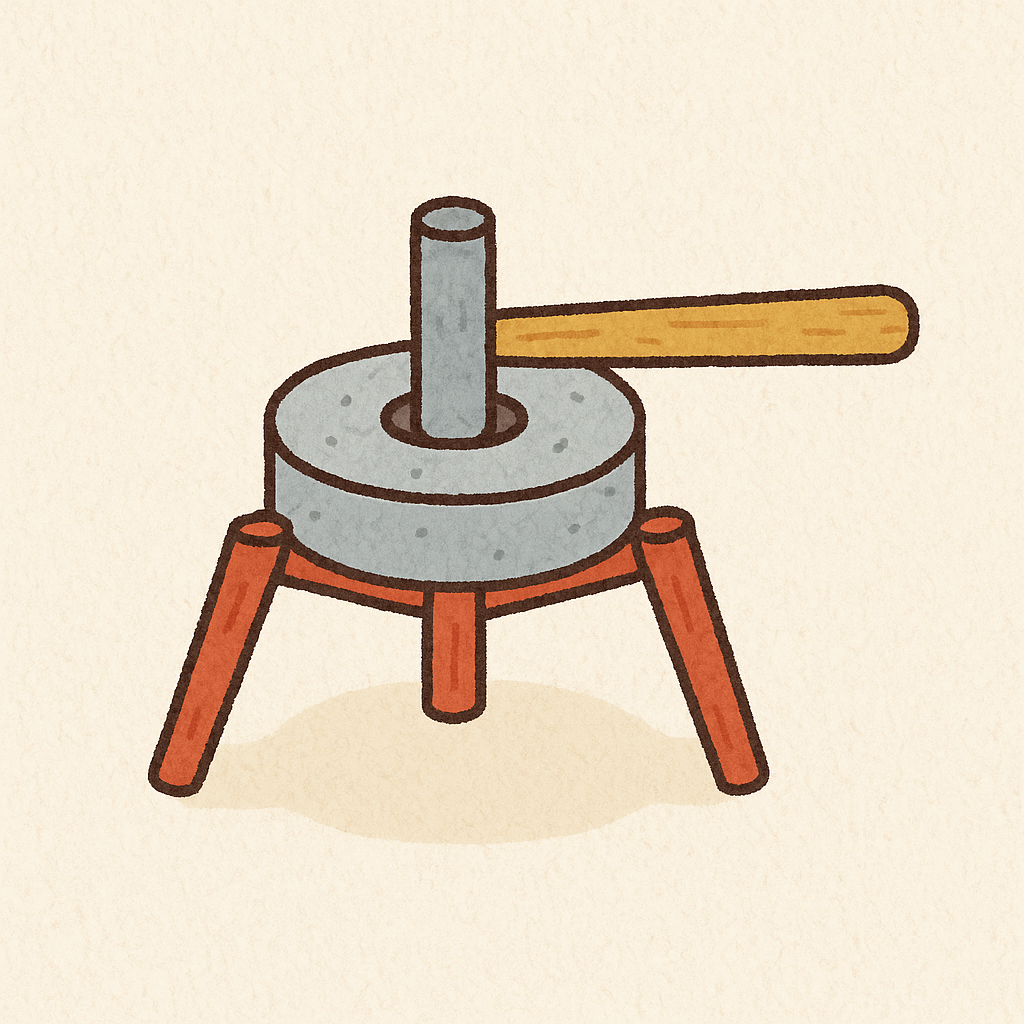
一般的に「歯ぎしり」といわれる症状で、「キリキリ」「ギシギシ」と音がします。
歯ぎしりの中で最も多いタイプで、歯を横にずらしながらこすり合わせ、きしむような音を発します。
主に睡眠中に起こり、歯がすり減ってしまう原因になります
クレンチング
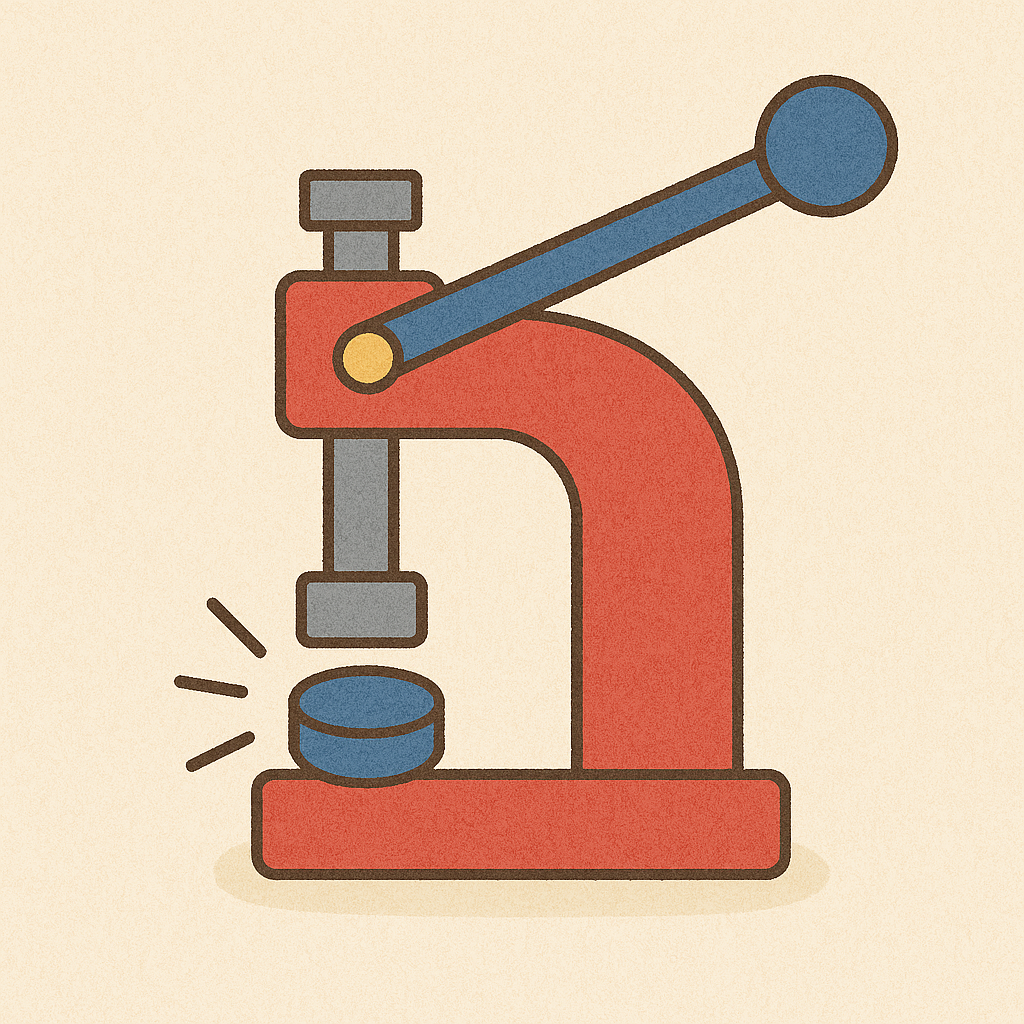
上下の歯に強い力をかけて押しつけ、噛み締めたままの状態が習慣化しているものです(噛み締め・食いしばり)。
音がしないため本人も周囲の人も気づかないことが多いです。
タッピング

上下の歯を「カチカチ」と小刻みに打ち鳴らすタイプの歯ぎしりです(カスタネットのような音)。
発症例は少なく、比較的お子さまに多いといわれています。
子供の歯ぎしり

子供が睡眠中に、ものすごい音をタッピング・クレンチング・グライディングをすると、「びっくり」心配になることでしょう。しかし、子供の歯ぎしりは一時的なもので、ほとんど心配ございません。子供の歯ぎしりは自然な現象、「歯の生え変わり」や「顎の骨の発育」にひつようなものだと考えられています。乳歯は永久歯と比較して柔らかいので、歯がすり減りやすいです。
子供は歯がすり減っても、永久歯が萌出いたします。周囲の組織も柔軟なので、歯ぎしりをしていても問題が出ることはほとんどないと判断されます。
耳が痛くなったり、顎関節症の症状が現れることがある場合には、治療を受けましょう。
<歯ぎしりをしやすい人>

- 向上心が強く努力家
- 知らず知らずのうちにストレスを抱えやすい
- 周囲に対して厳しく接してしまうことがある
- 忙しく時間に追われることが多い
- 目的意識がはっきりしていて、目標達成に前向き
- 負けず嫌いで粘り強い
- 緊張や集中から歯ぎしりしやすい
<歯ぎしりの原因>
歯ぎしりの原因は【習慣】【歯のバランス】【ストレス】といわれております。
【習慣的な要因】
職種によって歯ぎしりが多くなることも。プロ野球選手のように、瞬間的に歯を食いしばることが多い職業についている人は、それが原因で歯ぎしりと同じような症状が現れることがあります。
【咬み合わせが悪い】
治療で高さのあってない被せ物が入ったり、咬み合わせのバランスが悪い歯列方も歯ぎしりの原因になります。
【ストレス】
精神的なストレスが原因の歯ぎしりは、一番多いともいわれております。日中、極度な緊張や憂鬱な気分、不安な気持ちを感じると、睡眠中に歯ぎしりをしたり歯を食いしばることでストレスを解消していると考えられています。
【その他】
- 鼻・のどの炎症による場合
- 飲酒後の睡眠時
- 枕の高さが合わずに顎が上がった状態の場合
- 甲状腺機能亢進症などによる筋肉の緊張状態による場合
- 遺伝的要因
代表的な治療法
歯ぎしりの治療法は【対処療法】【咬み合わせ療法】【矯正治療】などがあります。
【対処療法】
マウスピースやプレートなどの防止装置を使用し、顎や歯などに加わる圧力を和らげて歯の摩耗・睡眠中の歯ぎしりを防止します。
マウスピース

歯ぎしりを防止する装置としてマウスピースの効果が代表的な治療になります。
きちんとあったものを使用すればしっかりと歯ぎしりを止めることも可能です。
しかし、マウスピースは歯ぎしりの症状を抑えるだけなので、原因となる治療(咬み合わせの安定化)も必要となります。
ボツリヌス療法
ボツリヌス療法は、ボツリヌス毒素を用いて筋肉の異常な収縮や神経の過活動を制御する医療技術です。この治療は、神経から筋肉への信号伝達を一時的に遮断することで、筋肉の弛緩を促します。 ボツリヌス療法の効果期間と最も効果が強まる時期については、以下のような特徴があります。
効果の発現期間
- 効果の発現: ボツリヌス毒素の注射後、効果が現れるまでには通常1~3日かかりますが、最大の効果が現れるまでには5~10日程度かかることと報告されております(MDPI) (Frontiers)。
- 比較的に治療効果が早く出やすい治療方法です。
効果の持続期間
- 持続期間: 一般的に、ボツリヌス療法の効果は3~4ヶ月程度持続します。
この期間は個人差があり、一部の患者では6ヶ月まで持続することもあります。
【咬み合わせ療法】
むし歯の治療やかみ合わせ、すり減った歯を元に戻すことで防止効果を得ます。 オクルージョン不良(かみあわせが安定していない)の場合、あっていない被せ物の交換やかみ合わせが安定するように治療します。
【矯正治療】
防止装置の使用と口腔周囲筋のトレーニングにより歯ぎしりを矯正します。 *マウスピース治療以外は保険外治療になります。
「こころ」から歯ぎしりを防止
歯ぎしりの多くはストレス性が原因で発症しています。したがって、「こころにゆとりを持たせる」ところから改善していくのもよいでしょう。

入眠直前、 口腔周囲筋(咬筋・側頭筋・口輪筋)・胸鎖乳突筋・僧帽筋・首周りの筋肉をマッサージし弛緩させる【ダラーンとさせる。】
潜在意識の中で【食いしばらない】【ぎゅって咬まない】と心の中で留めておくと、それだけでも効果があります。
【軽―い・余力を持たせる気持ち】で取り組み、寝る前にはゆったりとリラックスしましょう。
<フィックデンタルクリニック 院長 コメント>
歯ぎしりの治療は、歯科医師によっても考え方がさまざまで、「これがズバリ、原因で歯ぎしりの治療だ」という決まったものはないのが現状です。 まずは症状を把握し、歯科医院を受信のうえ、原因と思われる要因を取り除きながら相談して治療していきましょう。
参考文献
- From Toxin to Treatment: A Narrative Review on the Use of Botulinum Toxin for Autonomic Dysfunction
Lucas Rempel, Raza N. Malik, Claire Shackleton, Martín Calderón-Juárez, Rahul Sachdeva, Andrei V. Krassioukov - Use of botulinum toxin in the management of dystonia in Parkinson’s disease
Charenya Anandan, Joseph Jankovic,
